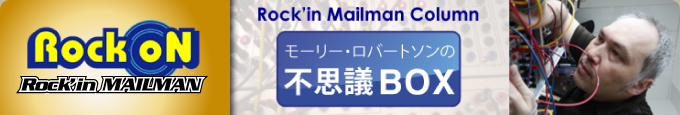【最終回】1973年の人間工学
今回はBuchla社がリメイクした「Music Easel」の基本を解説しよう。
公式サイトにフロント・パネルの大きな見取り図があったので早速キャプチャーした。
ぶっちゃけてしまうと、最初は使いにくい。通常のモジュラーよりコンパクトに圧縮されているためだ。だが慣れると、この小型シンセの利便性が明らかになる。
下半分のキーボード部分と上半分のコントロール・パネルの境目にパッチ・ベイがあり、ここが音作りの要となる。
パッチ・ベイを左から解説していこう。Pulse / Pressure / Pitch という3つの黒い穴が並んでいるが、これはどれもインプット。下のキーボード部分に同じもののアウトプットが並んでいるので、まずはこれらのペアをそれぞれ短いバナナ・ケーブルで接続する。この作業をやらないと、標準的な音は出ない。
Pulse
キーボードを押した時に「On」になるパルス。アルペジエーターが動いている時には連続的にパルスが発される。また、外部からMIDI Clockを受けた時にも、アルペジエーターの設定に応じてさまざまな分解能のパルスが放たれる(MIDI Clockの分解能に関しては、前回の記事を参照)。
Pressure
キーボードを押している指の面積に応じてCVが上下する。厳密にはプレッシャーではないが「強めに押し込んだ時には指の接触面積も大きい」という発想。
Pitch
キーボードやアルペジオの音程に対応したCV。これは絶対的なものではなく、あくまで相対的なもの。オシレーターの音程はその都度耳で設定する。デジタルなチューニング機能などは、ない。
Random Voltage
実験音楽専用のインターフェイスとして開発されたBuchlaのシステムでは、現代音楽で多用されていた「不確定性」が重要視されている。向かって右下の列にある白い出口はすべてランダムCVだが、一つ一つが独立したフレイバーのランダムとなっている。これらのランダムCVをトリガーする方法は「 keyboard / pulser / sequencer」という風にスイッチで3通り選べるようになっている。
まず「keyboard」のモードでは、タッチ・キーボードに触れたり、アルペジオで新しいステップが演奏される度にランダムCVが更新される。歴史的に間違った例えで言うなら「MIDI note on」を受ける度に変わるイメージだ。続いて「pulser」というモジュールはキー・タッチやアルペジオとは独立して動く簡易な「AR=アタック・リリース」式のエンベロープで、ほぼLFOと考えていい。このモードでは新しいアタックが発生するたびにランダムCVが変わる。3番目は「sequencer」モードで、パネルの左上にあるシーケンサーの各ステップでスイッチが「on」になっている時だけランダムCVが更新される。これだけを見てもBuchlaが1970年代当時からさまざまなグラデーションで「不確定性」を醸し出すことにこだわっていたのがわかる。対照的にMoog社の大口顧客は、ランダムCVを細かくカスタマイズすることにそれほどの執着を示さなかったことだろう。
さて、コントロール・パネルの右下側に並んでいる丸い「口」の数々だが、カラーコードで仕分けられており、慣れるとひと目で接続がわかるようになっている。まず、黒い「口」はすべてインプットで、それ以外はことごとくアウトプットだ。アウトプットからインプットという方向でしかパッチングはできない。
下側の青いアウトプットはどれも「pressure」であり、これは先に紹介したタッチ・キーボードに触れた指の面積に応じてCVが上下する。上の列は青、赤、黄の3色だが、同じ色のアウトプットは同一のCVを出力する。よく見ると、青→赤→黄→青→赤→黄と色が繰り返しており、最後に赤→黄となっている。この列の青は2つとも「sequencer」からのCV。赤は「ASR=アタック・サステイン・リリース」式のエンベロープから来るCV。そして黄色は先に述べた「AR」式のエンベロープである「pulser」からのCVになっている。
同一のCVアウトがリピートしているのは、それぞれの黒いインプットに最も近いところに位置することで、特別な短いツイン・プラグを斜めに挿せるようにするためだ。最低限のケーブルを使ってパッチを組むための人間工学が、このレイアウトで実現されている。
公式のチュートリアル動画でTodd Barton氏が各モジュールの機能を丁寧に紹介しているので、これ以降の解説は省略する。是非ご覧いただきたい。

Buchla Music Easel Quick Start & Overview
(画像クリックで再生)
さて、まだ触り始めたばかりだが雑感を述べると、持っていった先で電源をつないですぐに演奏ができるように、ロジックが圧縮されている。したがって通常のモジュラーに比べて接続手順には癖がある。また、メインのVCOとモジュレーション用のVCOが1つずつあるのみなので、個性のある音を目指すには多少のノウハウが必要だ。そしてMoog社の大きなアセットである「レゾナンス付きのローパス・フィルター」がこのシンセには、そもそもない。そこも発想を切り替えなくてはならない。ゼロからパッチングを始めても1分ほどで演奏ができるかわりに、捨てている要素も多分にあるのだ。
ごく簡単に3通りほどのパッチを組んでみた。どのパッチもDAWでコンプレッサーをかけた以外には、シンセからの生音である。
パッチ#1
ここではごく簡単な一定速度のシーケンスが繰り返している。シーケンサーのステップ数は「3」「4」と「5」なので、Moogや303のようなベースラインはなかなか組めない。そのかわり、タッチ・キーボードのアルペジエーターとの組み合わせで少しずつずれていくベースラインやメロディーラインは得意だ。

【パッチ#1をSound Cloudでチェック】
パッチ#2
シーケンサーの速度が一定ではない作例。AMのモジュレーションだと映画「スター・ウォーズ」の「R2D2」を彷彿とさせる音声がすぐに作れる。なお「Music Easel」の本体には実物のスプリング・リバーブが組み込まれており、ミックスのレベルを上げていくと簡単なパッチでも幻想的に「遠く」聴こえる。

【パッチ#2をSound Cloudでチェック】
パッチ#3
これはモジュラー・シンセサイザーの中でも珍しい効果。オーディオの出力をケーブルで入力へと接続、フィードバックのループを作ったものだ。マイクロフォンのフィードバックと同じように「ぴーっ」というハウリング音が発生するが、この音に歪みや多少のローパス・フィルターをかけることができる(ただしレゾナンスは無し)。また、このハウリングをスイッチで「外部音源」に設定すると、モジュレーターのVCOに対するリング・モジュレーションが起こる。物理的なリバーブのかかり具合を上げながらハウリングを調整すると、残響をかぶったハウリングがVCOをモジュレートし、その出力がさらにフィードバック…という複雑な音響が生まれる。スプリング・リバーブがハウリングと共に振動する感覚が指先に伝わってくるので、スリリングだ。
日本で言うと、関西で勢いのある「ノイズ・ミュージック」のシーンで歓迎されそうなパッチになった。乱暴な音だ。ここからさらに先へ行くなら、例えばKORGの「Monotron Delay」やハーモナイザー、外付けのフィルターなどをフィードバックのループに組み込むことで、延々と自己を更新する「不確定」な爆音を実現することもできるだろう。

【パッチ#3をSound Cloudでチェック】
「Music Easel」の魅力は、音源もCVもすべてアナログでありながら柔軟に音が設計できる点。そしてあくまでパフォーマンス専用の楽器を意図しているので、即興的に素早く音を作り替えていける点だ。タッチ・キーボードを使って「随意的に」演奏することもできれば、ロジックや音声をフィードバックさせた「自動演奏」もできる。
難点を挙げるなら、まずMIDIへの対応が不安定なこと。DJプレイの飛び道具としてならうまく行くだろうが、DAWでコントロールする「テクノポップ」には向いていない。また、ツマミやスライダーが脆弱だ。ライブで使い続けたら、遅かれ早かれ壊れる部分が出てくるに違いない。パーツの交換は日本だと厄介かもしれないので、購入する場合あらかじめ修理のプランを練っておいた方が無難だろう。まだ日本に輸入された実機の数は少ないが、時間をかけて触ってみる価値はある。
BuchlaとMoogは1960年代の同時期に開発された。両社はそれぞれアメリカの西海岸、東海岸を拠点にしていたため、「西海岸式」「東海岸式」と分類されることもある。Moog製品ではキーボードとの互換性が意識され、ELPやピンク・フロイドなどのロックバンドに愛用された結果、商業的にも大成功をおさめた。対照的に、Buchlaの製品は現代音楽の音響実験を推し進める「リサーチ用」の楽器として設計され、現代音楽の世界で最高峰の地位を築き上げた。YMOがBuchlaではなくMoogで音作りをしたのは、必然だったとも言える。見方を変えれば、YMOのファンこそBuchlaのパラダイムで作られた音に触れることで電子音楽の世界をぐるりと一周できるのだ。
☆ここでいきなり「YMOのアルバムですけど、半分ぐらいの音はSergeやBuchlaを使っていたんですよね」というインサイダーの声が聞こえてきた場合、筆者の過去の記憶はオセロゲームのようにごっそり白黒が反転してしまうだろう。
今回をもって、このコラムはいったん完結する。筆者は「西海岸式」に特化した形でモジュラー・シンセを解説してきたが、現在起きているモジュラーのリバイバルは全方位的におもしろい方向へと進化している。とにかくモジュラーは奥が深い。読者の皆さまにおいては、なるべく野太い音にこだわって、貪欲な音作りを目指していただきたい。
モーリー・ロバートソン プロフィール
日米双方の教育を受けた後、1981年に東京大学に現役合格。日本語で受験したアメリカ人としてはおそらく初めての合格者。東大に加えてハーバード大学、MIT、スタンフォード大学、UCバークレー、プリンストン大学、エール大学にも同時合格。1988年ハーバード大学を卒業。在学中に作曲家イワン・チェレプニンに師事、モジュラー・シンセを専門的に学んだ。現在はテレビ、ラジオ、講演会などで活躍中。
ニコ生に「モーリー・ロバートソン・チャンネル」を開催。